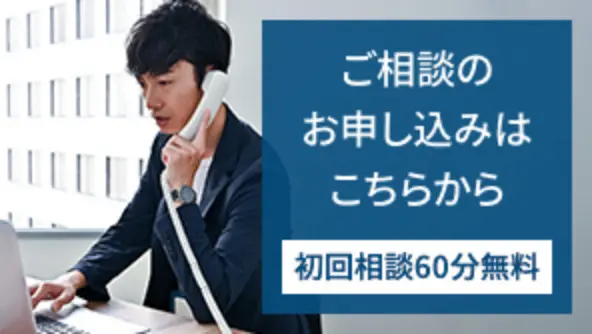ChatGPTは危険か?チャットGPTを安全に使う方法を弁護士が徹底解説

目次
1. ChatGPT(チャットジーピーティー)とは?
1.1 ChatGPTとは?私たちの仕事や生活をどう変えるのか
ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発した大規模言語モデル(LLM)を用いた対話型のAIです。人間のように自然な文章を生成し、文章の要約、翻訳、プログラミングコードの作成、アイデアの提案など、多岐にわたるタスクをこなすことができます。
ビジネスシーンでは企画書のたたき台作成や議事録の要約、個人の生活では学習の補助や旅行プランの作成など、私たちの生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めた、まさに革命的なツールです。
1.2 なぜ今「危険性」への理解が不可欠なのか
利便性の一方で、ChatGPTの利用には重大なリスクが伴います。安易な利用は、企業の機密情報や顧客の個人情報漏洩、意図しない著作権侵害、さらには法的責任問題に発展する可能性があります。
「知らなかった」では済まされない事態を避けるために、利用のメリットとリスクの両面を正しく理解し、適切な対策を講じることが、企業にとっても個人にとっても極めて重要になっています。
本記事では、法律の専門家である弁護士の視点から、利用のメリット及び危険性と対策を徹底解説します。

2. ChatGPTがもたらす3つの大きなメリット
危険性を解説する前に、ChatGPTがいかに有用なツールであるか、その主なメリットを3点確認しておきましょう。
2.1 メリット1:業務効率の劇的な向上
メールの文面作成、会議の議事録要約、報告書の構成案作成といった定型業務をAIに任せることで、人間はより創造的で重要な業務に集中できます。
2.2 メリット2:新たなアイデアや創造性の支援
一人では思いつかないような多角的な視点から、新商品のキャッチコピーや事業戦略のアイデアを提案してくれます。
思考の壁打ち相手として活用することで、新たなアイディアの発見や創造性の支援をしてくれます。
2.3 メリット3:情報収集・学習の高速化
専門的なトピックについて、要点を分かりやすく説明させることができます。
知りたい情報を対話形式で深掘りできるため、学習ツールとしても非常に優れています。
3. ChatGPTに潜む3つの危険性|利用規約から読み解く法的リスクと具体事例
ChatGPTの危険性(法的リスク)とは、①情報漏洩・プライバシー侵害、②著作権等の権利侵害、③不正確情報(ハルシネーション)によってトラブルになるリスクです。
ChatGPTの利用規約やプライバシーポリシーをもとに、想定される法的リスクを具体的な事例を交えて説明します。
3.1 利用規約確認の重要性とポイント
ChatGPTには、無料版、Plus、Pro、Team、Enterprise、APIなど様々なプランがあります。
無料版など個人向けの利用規約とビジネス向けの利用規約(OpenAIサービス契約)では、内容が異なります。
自社が利用しているプランの確認及び対象となる規約を正しく理解することが重要です。
3.2 危険性①:情報漏洩・プライバシー侵害のリスク
3.2.1 入力データが生成AIの学習に利用される可能性
入力したテキストやファイルが、AIモデルの性能向上のために学習利用される可能性があるかを利用規約や関連ポリシーに沿って確認することが重要です。
学習利用されると、情報漏洩やプライバシー侵害となるリスクがあるためです。
個人向けのChatGPTの場合は、利用規約に学習利用についての記載があります。その旨は、プライバシーポリシーにも次のとおり記載されています。
当社は、ChatGPTを支えるモデルの学習のためなど、本サービスの向上のため、お客様が提供するコンテンツ情報を使用する場合があります。当社モデルを学習させるためにお客様のコンテンツ情報を利用することを停止させる(オプトアウト)方法については、 こちらの手順(新しいウィンドウで開く) をお読みください。
これに対して、ChatGPT Team/Enterprise版の利用規約(OpenAIサービス契約)では次のとおり記載されており、明示的な同意がない限りはコンテンツが学習利用されないことを明示しています。
4.2. OpenAIの義務。OpenAIは、お客様にサービスを提供するため、適用法を遵守するため、OpenAIポリシーを施行するため、および不正使用を防止するために必要な範囲でのみ、お客様コンテンツを使用します。OpenAIは、お客様が明示的に同意しない限り、お客様コンテンツをサービスの開発または改善のために使用しません。
3.2.2 具体事例のご紹介(無料プランの利用による情報漏洩)
ChatGPTを利用して情報漏洩する事例としては、無料プランを利用して機密情報を入れるケースが考えられます。具体的には、次のようなケースです。
M&Aに関する情報について、企業の担当者が個人アカウントの無料版ChatGPTを使い情報入力を行いリスクの分析を行った。この情報がAIの学習に利用され、企業としての情報漏洩リスクを発生させてしまった。
情報漏洩・プライバシー侵害のリスクを防止するためには、無料版に機密情報・プライバシー情報を入れないことが重要です。
3.3 危険性②:著作権侵害のリスク
3.3.1 著作権侵害の利用は禁止されています
著作権を侵害するような情報を入力・利用することは、ChatGPTの規約でも禁止されています。
具体的には、他者の権利を侵害、悪用する方法で本サービスを使用することなどが禁止事項として定められています。禁止事項に違反した場合、アカウント停止等のリスクがあります。
3.3.2 リスク事例のご紹介(著作権のトラブル事例)
ChatGPTの生成物を安易に利用して問題が発生するケースとしては、具体的には次のようなケースが考えられます。
ChatGPTに生成させたブログ記事をそのまま公開したところ、内容が他社のコラム記事と酷似しており、著作権侵害であるとの指摘を受けた。
ChatGPTはインターネット上の情報をもとに回答を生成します。そのため、ChatGPTでの生成物を利用する場合は、他者の著作権を侵害していないかの確認が必要です。
3.4 危険性③:不正確な情報(ハルシネーション)のリスク
3.4.1 情報の正確性についてはOpenAI社は責任を取りません
ChatGPTは、事実に基づかない「もっともらしい嘘」を生成する「ハルシネーション」と呼ばれる現象が発生します。
ChatGPTを運営するOpenAI社はハルシネーションが発生しても原則として責任をとることはしません。
3.4.2 リスク事例のご紹介(存在しない統計情報の提供)
ハルシネーションの事例としては次のような事案が考えられます。
コンサルタントが、市場調査レポートを作成する際にChatGPTが提示した架空の統計データを引用し、クライアントに誤った情報を提供してしまい、信用を失った。
ChatGPTが生成した情報の正確性は一切保証されていません。
誤った情報をもとに行った判断によって損害が発生した場合、その情報を確認せずに利用したユーザー自身が責任を負うことになります。自己責任できちんと回答根拠を調査したうえで利用することが重要です。

4. ChatGPTの危険性を回避する具体的対策
これらの危険性を踏まえ、企業と個人がそれぞれ取るべき対策を解説します。
4.1 【企業向け】今すぐ実施すべき3つの対策
4.1.1 セキュリティの高い法人向けサービスの導入
企業が情報漏洩のリスクを低減して安全にChatGPTを利用するためには、入力データがAIの学習に利用されないと契約上保証されているプランを選択することが重要です。
この条件を満たすのは、ビジネス向けのプランである「ChatGPT Team」「ChatGPT Enterprise」、そしてシステム開発に用いる「API」経由での利用です。
そのため、企業でChatGPTを利用する場合は、ChatGPT Team又はEnterpriseのプランがおすすめです。
ChatGPTで個人データを処理する場合は、OpenAI との間で別途データ処理に関する補足事項(「DPA」)の契約をすることも可能です。
ChatGPT Team/Enterprise版では、SSO(シングルサインオン)による認証にも対応しているので外部からの不正なログイン対策も可能です。
4.1.2 社内ガイドラインの策定
安全なプランを選択するだけでは対策は十分ではありません。従業員一人ひとりが正しい知識を持って利用しなければ、リスクは残ります。
そこで重要になるのが、企業の状況に合わせてカスタマイズされた「社内利用規程(社内ガイドライン)」です。
- どのような情報の入力を許可し、何を禁止するのか?
- 生成された文章や画像をどのように扱うべきか(著作権等の確認)?
- 万が一、問題が発生した場合の報告ルートはどうするか?
これらのルールを明確に定めることで、従業員は安心して業務に活用でき、企業としても情報漏洩リスクを軽減できます。
たとえば、次のような項目を定めておくことが重要です。
① 目的・基本方針の明確化
なぜこの規程を定めるのか(例:情報資産の保護と生産性向上の両立)という目的と基本方針を明記します。
② 利用を許可するサービスの明確化
業務利用を許可するサービスを「ChatGPT Team」「ChatGPT Enterprise」などに限定して、従業員の個人アカウントでの業務利用を禁止します。
③ 入力禁止情報の記載
ChatGPTに入力してはいけない情報を具体的に列挙します。たとえば、会社の機密情報(顧客リスト、技術情報、財務情報等)を定義し、これらの入力を禁止します。
④ 禁止事項の明示
OpenAIの利用規約にある禁止事項に加え、会社の業務に関連する具体的な禁止行為などを記載します。
⑤ 生成コンテンツの取り扱いルールの記載
生成された情報は不正確な場合や、第三者の権利を侵害するリスクがあることを注意喚起し、必ず人間が内容の確認を行う必要があることを義務付けます。
⑥ 相談窓口の設置
利用方法に迷った場合や問題を発見した場合の報告・相談窓口を明記します。
4.1.3 従業員への継続的な教育
AIツールを導入したり、社内ガイドラインを策定しても、従業員に浸透しなければ意味がありません。そのため、定期的な社内研修や教育の機会を設けることが重要です。
AIツールは日々進化し、リスクの形も変わります。一度研修をすれば終わりではなく、定期的に情報セキュリティ研修を実施し、従業員のリテラシーを高く維持することが重要です。
4.2 【個人向け】自分の情報を守るための3つの鉄則
4.2.1 個人情報やプライベートな内容を入力しない
個人利用(無料版)のChatGPTは、入力情報について原則として学習利用がされます。
自分の氏名、住所、勤務先、家族構成、健康状態といった、個人を特定できる情報や他人に知られたくないプライベートな悩みなどを入力するのは控えましょう。
4.2.2 アカウントのセキュリティ設定を強化する
パスワードは長く複雑なものにし、可能であれば二要素認証を設定しましょう。これにより、不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。
4.2.3 生成された情報は必ずファクトチェックする
ChatGPTの回答を鵜呑みにせず、回答根拠を確かめてファクトチェックをするようにしましょう。
信頼できる情報源で裏付けを取る習慣を身に着けることが今後のAI時代で重要になってくると考えます。
5. よくある質問(FAQ)
5.1 Q1. 無料版のChatGPTは入力内容が学習に使われますか?
既定設定のままでは学習に利用される可能性があります。機密情報や個人情報の入力は避け、必要に応じて自動学習をオフにする設定に変更しましょう。
5.2 Q2. 企業利用はどのプランが安全ですか?
ChatGPT Team / EnterpriseやAPI利用が推奨です。これらは学習利用を行わない旨が規約で明確化されているためです。SSO等の管理機能も利用できます。
5.3 Q3.生成物の著作権や商用利用はどうなりますか?
ChatGPTの規約には利用者に権利帰属する旨の記載があります。しかし、生成AIの回答に直ちに著作権が発生するわけではありません。そのため、生成物をそのまま利用すると第三者権利の侵害リスクは残ります。公開・商用前に権利侵害をしていないかチェックが必要です。
5.4 Q4. ハルシネーションのリスクを減らすにはどうしたらいいですか?
根拠URLの提示を促すプロンプト、一次情報での裏取り、専門家レビューを組み合わせます。統計や法令は公式ソースで再確認しましょう。
5.5 Q5.企業が今すぐできる安全対策は?
入力データが学習に利用されないビジネスプランの選択、AIガイドラインの策定、社内研修です。各従業員の生成AIに対するリテラシーの向上も非常に重要です。
6. まとめ:リスクを理解し、ChatGPTを安全なパートナーに
6.1 これからのAI時代で重要なポイント
ChatGPTは、私たちの仕事や生活を豊かにする非常に強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、本記事で解説したような危険性を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。
リスクを恐れて利用を禁止するのではなく、安全な利用のためのルールを確立し、リテラシーを高めていくことが、これからのAI時代において重要です。
6.2 企業がChatGPTを利用するうえで重要なポイント
ChatGPTをビジネスとして利用する際には、特に以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 無料版を含む個人向けのChatGPTは入力情報がAIの学習に利用される危険性があり、ビジネス利用には向いていない。
- 企業でChatGPTを利用するなら、入力データが学習に利用されない「ChatGPT Team/Enterprise」を推奨。
- 従業員と会社を守るため、「社内利用規程(社内ガイドライン)」の策定と社内研修が重要。
6.3 弁護士がサポートできること
生成AIの利用規約は複雑で、法的な解釈を要する部分も少なくありません。また、社内ガイドラインにどのような規程を盛り込むべきかは、企業の状況によって異なります。
- 「自社に合ったガイドラインの作り方がわからない」
- 「利用規約を読んでも、法的なリスクを正確に判断できない」
- 「従業員への研修をどのように実施すればよいか悩んでいる」
このようなお悩みをお持ちの企業担当者様は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
無料相談実施中

企業法務チームに所属し、インターネット上の誹謗中傷対応、企業およびクリニックの顧問業務、使用者側の労働問題などを担当。
また、AI法研究会に所属し、生成AIに関する法律相談や企業対応にも取り組んでいる。